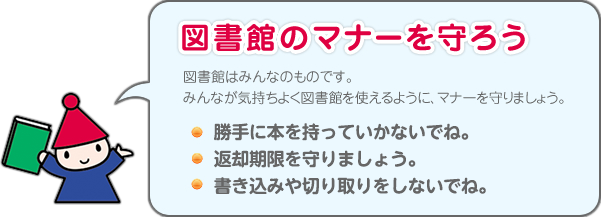調べ学習の手引きをご覧いただけます [PDF:1,437KB]
たくさんの本がならんでいる図書館は、情報の宝庫。上手な利用方法や、本を使った調べかたを知って、キミも「図書館の達人」になろう!
5-Daysこども図書館は、全国でもめずらしい、子どもの本を中心にした図書館です。
子どもと本を結ぶさまざまな行事を行っており、平成18年と令和2年に「子どもの読書活動優秀実践図書館表彰」を受賞しました。
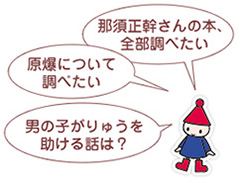
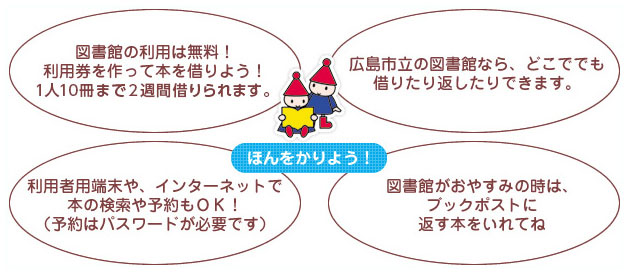
図書館の本は透明なフィルムやビニールのりを使って、傷みにくくしたり、本を管理するためのラベルもはります。このように、本屋さんから買った本を図書館で使えるようにする作業のことを装備(そうび)といいます。
図書館にあるすべての本に1冊1冊違う資料コードという番号があたえられています。この番号を使って、本の管理をします。現在こども図書館 では、コンピュータを使った本の管理をしていますので、1冊1冊の本の、資料コードや本を置く場所、分類(テーマ)などの情報をコンピュータに入力します。これを登録といいます。
装備(そうび)・登録が終わるとみなさんに読んでもらえるようになります。
資料コードを機械で読み取りやすくするためにバーコードラベルにして本にはります。
分類記号や図書記号が書いてあり、その本の内容(テーマ)や著者を表します。このラベルにしたがい、図書館の本は棚に並んでいます。
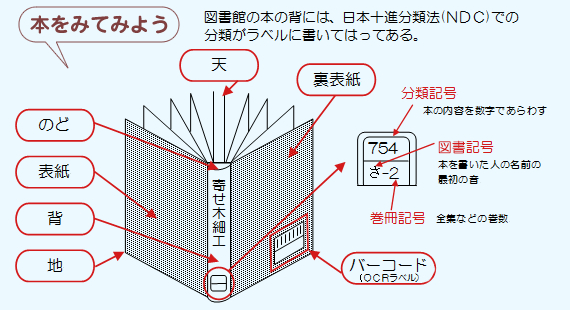
ラベルにはふつう3つの情報が書かれている。これをまとめて請求記号というよ。
図書館の本には「住所」があります。「住所」は本の内容(テーマ)によって、それぞれ異なります。「住所」は、本の背ラベルにある「分類番号」で表示されます。
日本の図書館はおおむね、日本十進分類法(NDC)というルールで分類記号を表示しているので、NDCを知っていると、とっても便利です。
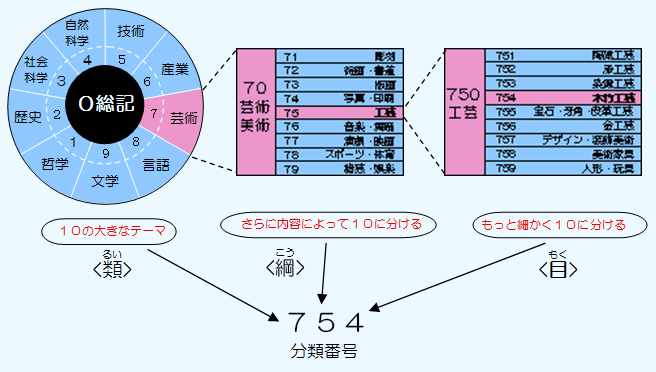
図書館での棚の並び方は、分類記号の000から999の順番で並び、さらにその中で著者名(図書記号)の五十音順に並んでいます。
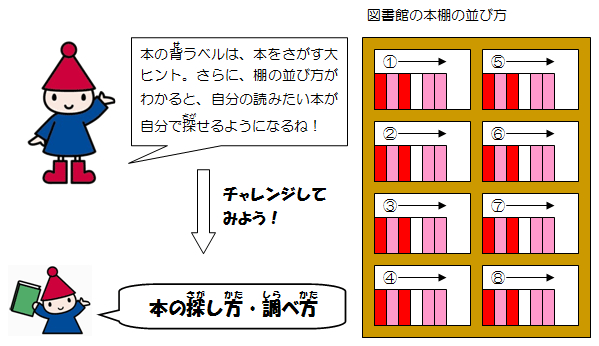
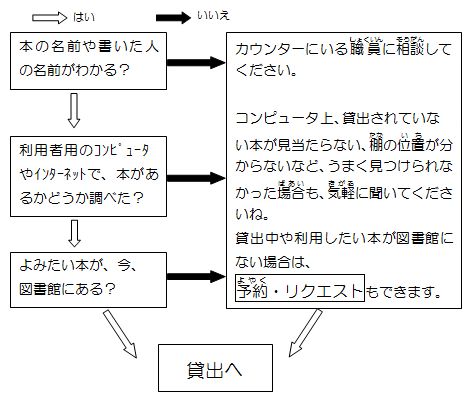
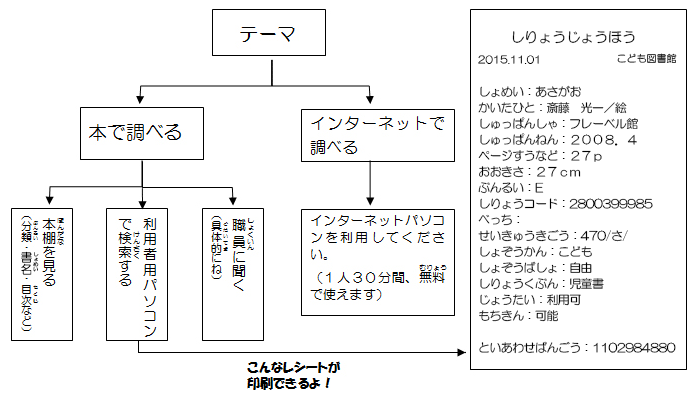
百科事典などは、巻末又はシリーズの最終巻に索引があります。
調べたい項目を索引で調べると、何ページにその項目があるかがわかります。
世の中の動きや最新の情報を知ることができます。
調べたい事項に関する大まかな知識を得ることができます。
※有害な資料(情報)や偽りのある場合もあるので、必ず複数のサイトを調べ、本でも確認しましょう。
※資料(情報)の速報性は、インターネット→新聞・雑誌→本(参考図書)の順です。
最新情報を知りたい場合は、この順番で探してみてね。